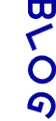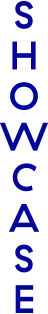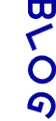Kyoto
2016.04.30
2015年の春から、一年とすこしを、コペンハーゲンで過ごした。ビザの延長申請が通らなかったので、2016年の春から夏にかけて家族の暮らす京都に舞い戻った。一年なんて私にとってはあっという間だったが、デンマークで長身の人間に囲まれ過ごすのに慣れていたようで、日本に帰ると久々に再会した人間は全員縮んで見えた。硬水とてきとうな石鹸で漱がれつづけてキシキシだった髪の毛は、軟水と風呂場にあった姉の高価なシャンプーをこっそり使ったことによってうるおいとかがやきを取り戻し、祖父母の家の台所は、使い慣れたはずの場所だというのに腰を折り曲げて皿を洗わねばならぬことに不満を感じさせ、わたしは何度もガス台の換気扇に頭をぶつけた。おしゃべりや広告、アナウンスにはじまり、街にあるあらゆる情報すべてが理解できすぎてしまってめまいを起こしたりして、その都度しばらく日本を離れて暮らしていたことを実感した。
なによりも一番時間の流れを感じさせたことは、出国前はピンピンしていた祖母が、二度の骨折と入退院ですっかりしっかり歳を取ってしまっていたことだった。姿勢わるくノロノロ歩くのは老人の証拠で、私はそうはなりたないんやと誰よりもシャキシャキと颯爽と歩を進めていた祖母は、歩行器にすがるように捕まってヨタヨタと歩くことしかできず、外出は車椅子のお世話にならねばならなくなっていた。かつての祖母を思い出して涙が出そうになってしまう。一年どころか、半年前に一度帰国した時とまるっきり様子が違い、一人で歩けず話にものっそりとした反応しかできなくなくなった祖母を見るたびどうしても気持ちが追いつかず、笑顔で接することはできても、そのあと落ち込んでしまうことが続いた。
誰でもこうして老いることをどうして想像したことがなかったんだろうか。祖母は永遠に颯爽として格好いい”幸子さん”(おばあちゃんと呼ばれることを嫌って下の名前で呼んでねとある日から言われて以来そうしている)であり続けると思っていた。そんなはずないんやな、と細ってしまった祖母の着替えを手伝う。
老いと付き合うことにすでに覚悟を決めた母は、既にその状態に慣れ始め、祖母の介護は日常に組み込まれつつあった。落ち込む暇があったら手伝って頂戴といった様相で手際が良い。常に家にいることはできないので、私にできることと言ったらお出かけの機会をもうけて気分を変えてもらうことだろうと思い、時間があるかぎり祖母を外に連れ出した。初めての車椅子でのおでかけ先は、植物園になった。
着飾ることが好きだった祖母は華やかな服をたくさん持っている。出歩くときに着飾ると嬉しそうにするのは相変わらずだ。眉毛を描き、むかし贈った、花びらをはたくと頬紅になるちょっと特別な化粧道具をつかって紅をさすと、嬉しそうにしてくれた。植物園の薔薇は満開だった。祖母は顔をくしゃくしゃとして喜んでいた。園内を少し、歩行器を使って散歩した。これで今晩はよく眠れるといいねと話す。
植物園の帰り道、和菓子屋さんがあって、そこで冷たいお茶とおやつをいただこうとするが、店の入り口には狭くて高い段差があって、乗り入れが難しい。車椅子の扱いに慣れないもので、段差にぶつかったり急発信をしてしまったせいで、祖母の顔はゆっくりと怯えて固まった。漫画に出てきそうなくらいおおげさな顔だったので笑いそうになってしまったけど、すぐに怖い怖いと声をあげるのではなく恐怖にもゆっくりと反応するようになったことに気づいて悲しくなった。
だからどうという話でもない、日本を離れている間にすっかり変わってしまった祖母と介護にだんだん疲れていく家族を見ると申し訳なさがつのり振り切るように金沢に移動し、しかし罪悪感が重たくのしかかってどうしようもなくなって京都に戻ったりを繰り返した。そして東京にも行き、そしてコペンハーゲンに戻った。およそ半年の間日本にいてその半分ほどの時間を京都で家族とすごした。一緒にいる限りは楽しい時間にしようと思い、どこかに連れ出したり、お菓子を一緒に食べたり、料理を作っておしゃべりして過ごした。家族と遠く離れて暮らす全ての人が悩むことだと思うけれど、私は私なりに答えをさぐって、祖母も、家族も、そして自分も大切にできる方法で一緒にいる時間を過ごせたんじゃないかと思うことにした。正解はわからない。
改めて家族を思う時、植物園に出かけた日のことをまず思い出す。植物園から和菓子屋までの道のりと、おどろいた幸子さんの顔。晴れた北山通は交通量も多く、車椅子のブレーキを強く握りしめながらタクシーを待った。少しの段差で幸子さんの乗った車椅子が前に滑り出さないか、心配でたまらなかった。初めての介護らしい介護に覚悟は決めた家族も、思った以上の負担に皆ずいぶん戸惑い、疲弊した。祖父は祖母よりは手がかからない分、ほったらかしにされて拗ねていた。
友達と「大人のピークっていつなんかな」という話をした。「自立した老人が極限の大人じゃない」という仮説に至ったことがあった。ふとしたきっかけで、祖父母がどんどん子供に戻っていく。母が祖父母のオムツを買い、まるで子供をあやすように眠れない祖母を慰める。不思議な気持ちになる。私はもう子供じゃないと、今まで何回も自覚する瞬間はあったけれど、今までのどんな時よりも強く感じる。祖父母はどちらもまだ生きているのに、一緒に遊んだ思い出が走馬灯のようにあたまを駆け巡って離れない。
遠くにいて普段何もできないぶん、帰省したらできるだけたくさん喋って、少しでいいからいつもと違う空気を運んでちょっとでもいい気分になってもらえるように過ごしたい。長くなったわりにまとまらない話になった。家族の話はいつも難しい。